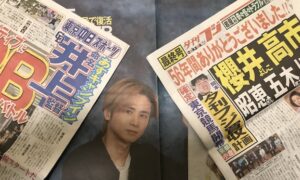産科医療機関4施設に年1億円補助 高崎市に聞く
松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵
最新記事 by 松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵 (全て見る)
- 24年後もサバイバー 中島瑞果(2)生き残るために - 2026年2月11日
- 24年後もサバイバー 中島瑞果(1)PTA会長”みずっち” - 2026年2月8日
- 文化人放送局が認否保留 著作権侵害訴訟始まる - 2026年1月25日
進む少子化などで全国的に産科医療機関の数が減る中、群馬県高崎市(富岡賢治市長)は独自の支援を行なっている。産科医確保のために市内にある病院や診療所に直接補助金を交付している。現在、厚生労働省で実施されている妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会でも、周産期医療体制の維持のために産科医療機関への早急な支援の必要性が主張されている。国の対策を”待っていられない”地方自治体の取り組みは、そうした議論に影響を与える可能性がある。高崎市に支援の目的や効果について聞いた。
◾️2年連続で1億円の支援
高崎市では2023(令和5)年度から、産科医確保のために病院に4000万円、診療所に2000万円の補助金を交付している。この取り組みは予算案に盛り込まれた時点で注目を集め、各メディアで報じられた(朝日新聞DIGITAL・産科医確保に補助制度創設へ 高崎市 ほか)。
24時間体制で出産に対応できる民間の医療機関は当初、1病院4診療所であった。しかし、2023年3月末に1診療所が分娩の取り扱いを中止したため、残る4つの機関に補助を実施することとなった(日本経済新聞電子版・群馬・高崎市、産科医など確保に1億円助成 23年度)。
2023(令和5)年度の予算案では産科医等確保支援補助金として1億円が計上された。その趣旨は「少子化やコロナ禍の影響を受ける市内の分娩を扱う産科では、医療従事者が恒常的に不足し、24時間の対応など必要な体制の確保が課題となっていることから、医師等の確保を支援し、安心して子供を産み育てられる環境整備を推進する。」とされている(高崎市令和5年度・当初予算の概要及び主要事業 p17)。
2024(令和6)年度も同様の名目で1億500万円を計上。500万円の上昇分に関しては「令和6年度は、消防用設備のスプリンクラー設置に対する支援を追加する。」との説明がある(高崎市令和6年度・当初予算の概要及び主要事業 p18)。結果として、高崎市の産科の病院1施設、診療所3施設へ2年連続で合計2億500万円が補助として交付されたことになる。これは「真水を注入」する直接的な支援であり、同市の抱く危機感が尋常なレベルではないことを思わせる。
同市では支援を開始したきっかけ、動機について「産科医への支援については、現状の本市の産科医療を取り巻く環境を踏まえるとともに、令和4年度限りで本市の総分娩数の約1割を担っていた産婦人科において、分娩を取り扱わなくなったこともあり、本市の産科医療に対する今後の見通しを考慮し本支援を実施することとしたものです。」(同市保健所(保健医療部)保健医療総務課)と説明する。
また、この補助について制度として確立されたものか、来年度(2025年度)以降も継続的に行うかを聞くと、「当該支援については、『高崎市産科医等確保支援補助金交付要綱』に基づく支援としておりますが、あくまでも本市の産科医療を取り巻く環境を踏まえ実施をしているものであり、今後の情勢により臨機応変に対応するものと考えております。」(同課)との回答が得られた。
◾️少子化と赤字経営の産科医療機関
少子化の影響を受けて全国の産科医療機関は年々、減少傾向にある。産婦人科、産科を標榜する病院は2008(平成20)年度の1496施設から毎年減り続け、2023(令和5)年度には1254施設と15年でおよそ16%減少している。同様に一般診療所は3955施設から3092施設へ、約22%の減少である(厚労省・令和5(2023)年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況 結果の概況 p11)。
出生数の減少も著しく、年度ではなく年単位の推移を見ると、2008年は109万1156人(e-stat・人口動態調査 人口動態統計 確定数 出生)で、2023年は72万7277人(厚生労働省・令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況)と33.5%減少している。産科医療機関の減少はこの出生数の減少に伴うものであることは明白。
経営面でも厳しい状況が続く。2024年11月に日本医師会総合政策研究機構は、日本産婦人科医会会員で分娩を実施している産婦人科、産科診療所(n=1000)を対象にアンケート調査を実施し、その経営状態を明らかにしている。そこで法人に経常利益について聞くと(n=191)、補助金を含んだ場合の赤字施設は2022年度で41.9%、2023年度で42.4%に達した。補助金を含まなければ、これらの数値はそれぞれ46.7%、47.2%となる(日本医師会総合政策研究機構・日医総研ワーキングペーパー 産科診療所の特別調査 p9)。
このような状況に対して、日本産婦人科医会の前田津紀夫副会長は第6回 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(2024年12月12日)の場で「…悠長なことを言っていると本当に医療機関がなくなってまいります。…全国の産科施設の4割がここ2年で赤字経営をしています。4割ですよ。」「…保険化ということが新聞の見出しに出る度に『やめる』と言い出す仲間がいます。そうした中でどうして安全な医療供給体制が整備できますか。…3年後、4年後に何かをやってくれたとしても、その頃には潰れてしまっています。自治体によっては産科医療機関に対して、500万、1000万出している市があるんです。群馬県にございます。そういった医療機関が減っているところは自治体が危機感を持っています。それを国の会議体が、機関が危機感をもたずにどうするんでしょうかと、私は常々思っています。」(参照・分娩費用の保険適用化 26年度導入見送りへ)と警鐘を鳴らした。
◾️国の支援を待って…は「時期逸する」
前田副会長が言及した群馬県の自治体が高崎市である。同市は2024年12月末時点で人口36万5972人(高崎市・人口及び世帯数)を擁する県内最大の都市である。その高崎市に24時間体制で出産に対応できる産科医療機関はわずかに4施設しかない。
24時間体制で出産に対応できる公的施設のない高崎市は既存の民間施設に産科医療を継続してもらう必要がある。仮に4つの施設が閉院ということになれば、出産を控えた高崎市民は市外の施設に頼るしかない。36万都市で安全安心なお産が出来ないということになれば行政としての責任が問われる。
高崎市に他の行政との連携について聞くと、国との関係はもちろん、群馬県との連携についても「特にございません。」(前出の同市保健所(保健医療部)保健医療総務課)とのことで、支援策はあくまでも市が独自で、市だけの力で行っている。本来、こうした国民の生命や健康に関わる事項は国が主導すべきところ対策が遅れている点をどう考えるのか聞くと「現状、国における明確な支援策が示されていない中、それを待っていたのでは時期を逸してしまう懸念とともに、本市の産科医療の現状を踏まえ、本市独自の支援を行っているものです。」(同課)とのことであった。
前出の日本産婦人科医会の前田副会長の検討会での「…悠長なことを言っていると本当に医療機関がなくなってまいります。…3年後、4年後に何かをやってくれたとしても、その頃には潰れてしまっています。」という発言を、少なくとも高崎市においては正面からとらえていると言って差し支えない。
◾️保険適用化についても留意する高崎市
政府は2026年度を目処に分娩費用の保険適用化を閣議決定した。これに日本産婦人科医会などが強く反発。保険適用化が進めば、経営が成り立たないとして閉院する機関が続出するとしている。このため、2026年度導入は見送りとされた(参照・分娩費用の保険適用化 26年度導入見送りへ)。
この導入見送りについては正式には発表されていないため、高崎市でも導入の可否には注目しているという。そこで、最後に保険適用化が実施された場合の影響について聞くと、「国における産科医療機関への何かしらの支援策が必要であると考えている。」(同課)との回答であった。つまり、保険適用化によって産科医療機関の負担が増加し、現状以上に新たな支援が必要になるという見たてをしているのである。
国に先んじて産科医療機関への支援を行っている高崎市の政策は、周産期医療体制の維持のために1つの参考、指針となる。検討会において、まだその点が取り上げられていないのは現状把握の上でも問題があるように感じられる。