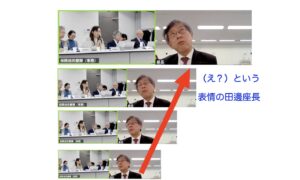生成AI使ってサイト運営 ライターの未来
松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵
最新記事 by 松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵 (全て見る)
- 24年後もサバイバー 中島瑞果(2)生き残るために - 2026年2月11日
- 24年後もサバイバー 中島瑞果(1)PTA会長”みずっち” - 2026年2月8日
- 文化人放送局が認否保留 著作権侵害訴訟始まる - 2026年1月25日
令和電子瓦版では2025年から、一部、生成AIの力を借りてサイト運営を行なっている。記事を書き上げた後に間違いがないかをチェックする校閲を生成AIに託すもので、誤字脱字の発見、冗長・重複する表現を指摘するなど、新聞社の校閲の役割を果たしている。既にAIによる記事生成が始まっており、記者の仕事は大部分、AIに取って代わられる可能性があると思う。AIが代用できない仕事をどれだけできるかが、記者・ライターが生き残る道と思える。
◾️新聞社では三重のチェック
当サイトでは2025年から、記事としてアップする前の原稿をChat GPTに校閲させている。原稿の発案から構成を考えて書き上げるまでは全て人力であるが、一応の完成の後、Chat GPTに全文の校閲を命じる。
現在、1本の記事は概ね3000文字。原稿用紙8枚程度になり、そこで1つのミスも許されないというのはかなり無理がある。新聞社であれば、記者が書いてデスクが読み、場合によってはリライトし、整理部も目を通して最後に校閲が国語上の問題をチェックと、概ね三重のフィルターを通して商品化(新聞発行)される。さすがに単純な間違いはほとんど見ないが、それでも事実関係を勘違いしたままチェックをすり抜けて記事になることがある。
当サイトのような個人が運営するサイトでは、取材・出稿・チェックとすべて1人がこなさないといけない。1本3000文字の記事を1か月に20本程度アップしている中でノーミスなどということはあり得ない。お恥ずかしい話であるが、当サイトの昔の記事を読むと明らかな誤字(特に誤変換)が見つかることがある。そういう場合はすぐに修正するが、(読者は気付いていたんだろうな)と思うとかなり恥ずかしい思いがする。
以前からその点で限界を感じていた部分があったが、校閲に生成AIを使うと「何だ、AIが書いているのか」と思われるのではないかとの不安があり、生成AI使用には慎重に構えていた。しかし、校閲に使うだけならクリエイティビティの部分には問題はなく、ミスがなくなればそれは読者のためにもなるということで新年からの使用を決めたという次第。
◾️校閲に使ってみると…
実際に使用してみると、これが便利な代物である。具体的にはある記事で「同様に」とすべきところを「同様に同様に」となっているなど、単純なミスの指摘があった。この種のミスはPCで記事を作成していると必ずと言っていいほど発生する現象で、キーのミスタッチで変換の候補が出た時に間違って確定させてしまうことで起きる場合が多い。そして、誤字ではないので書きながら違和感を覚えないので見過ごしてしまいがち。こういう指摘は非常にありがたい。
それ以外にも表現が厳しいものであった場合には穏やかな表現にしてはどうかと提案してくることもある。そうした様々な提案を1つ1つ書き手としてチェックし、受け入れる場合は受け入れている。指摘を受けて変更するのは2割程度か。
生成AIもまだまだ精緻さが不足している場合が少なくない。たとえば、文章表現の変更の提案では、素人のような指摘をしてくる。当サイトでは、筆者(松田隆)の文体はいわゆる「~である」で統一している。一般に文章は「だ、である」と「です、ます」に分けられるが、「だ」と「である」も異なる文体であり、前者がカジュアル、後者がフォーマルな表現と言っていい。
それが「である」の記事に対して「だ」で修正してくることがある。そういう時は「である、で統一しているのに、何で『だ』が入るんだ」と生成AIに聞くと「統一ルールに従うべきでした」と言ってくる。そのあたりは生成AIの学習がそこまで進んでいないということなのであろう。
◾️時代は記事作成もAI
校閲機能に限り使用を始めてから1か月ほどになるが、新聞社は校閲部門をすべて生成AIに替えた方がいいのではないかと感じている。実は筆者の在籍していた日刊スポーツでは経営のスリム化のためか、校閲部門はかなり早い時期に消滅している。一般紙ではまだ残っていると思うが、校閲の人件費は生成AIの使用でかなり抑えられると思う。
一部では既に導入しているのかもしれないが、新聞社が少しでも生きながらえるためにはできるところから合理化していくしかない。今まで2人がかりでやっていたところを1人が生成AIを使えば人件費は半分になる。実際にChatGPTとの連携で文章の修正を行うサイトもある(User Local 文章校正AI)。
もちろん、時代はもっと先を進んでいる。BloombergはCyborgというAIを活用システムで、企業の決算報道に関する金融ニュース記事の作成支援を行なっている。その種の記事は膨大なデータが公表されるために人力でそれを解析するのはかなり手間がかかる。その点、AIにやらせれば分析能力も高い、ハイクォリティな記事を作成できる(Pamper Me・What Is Bloomberg’s Cyborg AI? | AI Tools | Artificial Intelligence In Journalism Case Study)。
同じようにスポーツの結果なども事実関係だけを伝えるのであれば、AIに任せておいた方が間違いは少ないと思われる。試しにサッカーのチャンピオンズリーグの記事を書くように命じてみた。具体的には「チャンピオンズリーグの2月4日時点でのスタンディングと、今後の見通しをまとめて。」という一言だけの指示。
チャンピオンズリーグは今年から開催方式が変わり、ベスト16入りを目指すプレーオフ(9位~16位)が2月12日から第1レグが始まる。生成AIは新しいシステムの仕組みと、プレーオフの見どころ(RマドリードvsマンチェスターC)の紹介を、スラスラと書いてきた。その内容はスポーツ新聞のサッカー面の大会前の煽りのようなタイプであるが、十分に商業ベースに乗るレベルにあった。
◾️著作権法での制約が必要か
こうした現実を突きつけられると、やがて記者やライターの仕事は生成AIに奪われてしまうのではないかと不安を感じるようになる。もちろん、当サイトのような個人運営の小サイトでは生成AIを使用すれば1人で1日数本から10本程度の原稿をアップすることが可能になり、大きなビジネスチャンスになり得る。こうしたことを危機と感じるか、ビジネスチャンスと前向きに捉えるかで今後のあり方も変わってくるに違いない。
これまではまとめサイトがやっていたようなことを個人でもできるようになるということであろう。もちろん、オールドメディアも黙っているはずもなく、AIが学習する中から「ウチのメディアは学習材料とするな」と言い出すことは十分に予想される。
細かい話をすれば、現行の著作権法上の解釈は、AIが過去の記事などを学習するのは同法30条の4第2号の「情報分析」に該当するため、利用できると判断しているものと思われる。しかし、その学習によって生成されるものが、オリジナルの記事の著作権を持つ会社の利益が損なわれるのであれば、30条の4但書で規制すべきと思われる。
【著作権法30条の4】
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
…
2 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
◾️生成AIとの共生
この先、新聞社や出版社は生成AIをうまく使いこなし、記事作成コストを極力抑え、かつ、大量の情報を出すことが生き残りに繋がる。それはテレビなどのメディアでも事情は大きくは変わらないはず。
当サイトもそうした時代に取り残されないように、クリエイティビティが毀損されない程度に、生成AIと共生していく道を探っていきたい。