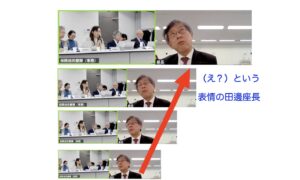CM”便乗引上げ” フジ戻らない広告収入の恐怖
松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵
最新記事 by 松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵 (全て見る)
- 24年後もサバイバー 中島瑞果(2)生き残るために - 2026年2月11日
- 24年後もサバイバー 中島瑞果(1)PTA会長”みずっち” - 2026年2月8日
- 文化人放送局が認否保留 著作権侵害訴訟始まる - 2026年1月25日
フジテレビから撤退したCMは、元の状態に完全には戻ることはないとの懸念がある。元タレントの中居正広氏の女性トラブルに端を発した一連の騒動で、フジテレビはほとんどのスポンサーからCMを打ち切られている。この事態はトラブルが直接的な原因であるのは明らかであるが、同時にテレビという媒体の価値低下も背景にあるように思われる。
◾️オールドメディアの没落
1月17日の港浩一社長(当時)の1回目の記者会見直後に、トヨタや日本生命などがCMを差し替える事態となり、その後、雪崩を打つかのように続々とCM差し替えが行われた。一時はAC ジャパンの広告が延々と流れたが、その後は番組宣伝などに変わりつつある。
1月20日までに少なくとも75社が同様の措置をとったとされる。CMを継続しているのは「高須クリニック」や「夢グループ」、再開したのは「キンライサー」など、ごく限られた企業、法人しかない(ORICON NEWS・フジ、CM差し替え急拡大の裏で継続、再開を決めた企業の思い 中居正広氏引退騒動の余波)。
3月末に予定される第三者委員会の調査結果の発表を受け、フジテレビが体制を一新するなど大きな変革があればスポンサーは戻る可能性はあるかもしれないが、ことはそう単純ではない。
今回、フジテレビからCMを引き上げた企業の中には、テレビCMの費用対効果も併せて考えた企業があっても不思議はない。インターネットの伝播力、世論に与える影響が強くなり、テレビや新聞が「オールドメディア」と揶揄される時代である。揶揄される理由は政治的偏向、真実を伝えないなど報道の内容がメインと思われるが、媒体そのもののパワー、テレビなら視聴量、新聞なら発行部数の急激な落ち込み、その影響による広告掲載媒体としての魅力の低下がある。
◾️テレビの価値の相対的な低下
電通は毎年、日本の媒体別広告費を発表している。ネット広告がほとんど存在しなかったに等しい1997年、テレビの広告費の総額は2兆79億円であった。これは新聞、雑誌、ラジオ、テレビなど主要な媒体の広告費の33.5%を占め、SP(セールスプロモーション)広告(DMや看板、POP広告など)、プロモーションメディア広告の34.0%に次ぐ地位にあった。当時の媒体別構成比は新聞21.1%、雑誌7.3%。インターネット広告は総額で60億円、構成比では0.1%に過ぎなかった。
ところがインターネット広告は上昇を続け、2019年に2兆1048億円を記録、テレビ(地上波+衛星メディア)の1兆8612億円を上回った。2020年には2兆2290億円で、SP広告・プロモーションメディア広告の1兆6768億円を抜く。2023年には3兆3330億円まで増え、テレビの1兆7347億円の1.9倍以上となった。
ネットがテレビの広告費を逆転した2019年はネット時代の到来を象徴する年となった。その4年後には広告費は1.6倍にまで膨らんでいるのである。一方、テレビの広告費が最も多かったのは地上波に限れば2000年の2兆793億円で、この年の衛星メディアと合わせた2兆1059億円と比較すると、2023年は82.4%と2割近い減少となっている(以上、電通・日本の広告費2023)。
テレビの広告費が増加しないのはごく単純な話で、たとえば関東圏の民放はキー局が日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビの5局。24時間放送する中で、1時間あたり平均10分のCMタイムがあるとすれば240分、5局分となると1200分である。この1200分しか稼ぐ場がなく、広告量は上限が設定されている。
一方、インターネットは次々に新しいサイトが生まれ、そこに広告がつくことが可能になり広告料の上限という天井は存在しない。当サイトのように個人で運営するサイトにも広告が掲出されており、広告量は年々上昇していく下地はある。パイ自体が大きくなるネットに対して、パイの大きさは変わらないテレビでは、最初から勝負にならないのは見えている。
◾️資生堂 しまむら ボンカレー
テレビ局が天井を打たれている中、広告収入をアップしようと思えば単価を上げるしかない。単価を上げるには視聴率を上げるしかないが、現代の若者はテレビよりネットを見る傾向がある。テレビの利用時間を見ると、10代は2000年には1日180分近くあったものが、2015年には70分程度に減少。20代も約180分から約110分に減少している(総務省・令和元年版 情報白書)。
10代・20代のテレビ離れとネット利用の増加は、上記の白書でも指摘されている。若者のテレビ離れが顕著な状況で、CMの単価を上昇させることなどできない相談。その結果、2023年のテレビ広告費は2000年比で約8割に減少する事態となった。
スポンサー企業もそうした媒体の動きには敏感である。1980年代、派手にテレビCMを打っていた企業に化粧品の資生堂がある。ゴールデンタイムに数多くのCMを流し、そのキャンペーンソングに採用した曲はほとんどオリコンで上位に入るほどの影響力を見せた。
ところが、その資生堂は2020年に広告媒体費の90%以上をデジタルにシフトすると表明した。当時の魚谷雅彦社長(現・取締役代表執行役会長CEO)は費用対効果のマーケティングを行うこととしている。同社の当時の広告媒体費は約2500億円で、そのうち半分の約1250億円がテレビCMの費用であった。90%以上をデジタルにシフトするとテレビCM分は250億円以下に、即ち5分の1以下になってしまう。
テレビCMは消費者のターゲット層を細かく絞り込むことが難しい。その点、ネット広告はターゲット層を絞り込むのは容易で、費用対効果を考えればネット広告の方が遥かに優れているという判断をしたものと思われる(以上、デイリー新潮・資生堂が広告媒体費の90%以上をデジタルにシフト 苦境のテレビCMはどうなるのか)。
資生堂以外にも、大塚食品のボンカレーは2013年にテレビCMから撤退している(日本経済新聞電子版・CM撤退の「ボンカレー」、ネット動画へ誘導強化の秘策)。衣料品大手のしまむらもテレビから撤退して、ネット広告へとシフトしている(JCAST・しまむら「脱テレビCM」でも業績好調 デジタル広告へシフト「低コストで売上効果も十分」)。
◾️フジ幹部は裸の王様
このようにテレビの広告媒体としての魅力、パワーはかなり落ちていることが分かる。筆者は専門学校で講師を務めているが、18歳から20歳の若者がいかにテレビを見ないかを日々実感している。地方から出てきた学生は新聞を定期購読しないし、テレビも持たない。テレビ受像機がなければNHKの受信料を支払う必要はなく、情報はスマートフォンから得られるので特に不便になることもない。
今回の各スポンサー企業のフジテレビからのCM引き上げは、直接のきっかけはフジテレビが信頼を失わせる行為にあっても、その背景にはテレビCMに以前ほどの魅力がなくなっていることは見逃せない。各企業が「この機会にテレビCMを減らそう」と考え、CMを減らしても売り上げには影響がなければ、再開しない選択肢は十分に考えられる。
フジテレビはそうした時代の動きをどこまで感じているのか。トラブルの一連の対応を見る限り、少なくとも幹部は裸の王様であることに気付いていないように思える。