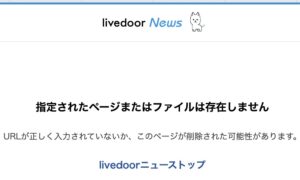代理出産より子宮移植 生殖補助医療の行方(前)
松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵
最新記事 by 松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵 (全て見る)
- 24年後もサバイバー 中島瑞果(2)生き残るために - 2026年2月11日
- 24年後もサバイバー 中島瑞果(1)PTA会長”みずっち” - 2026年2月8日
- 文化人放送局が認否保留 著作権侵害訴訟始まる - 2026年1月25日
生殖補助医療の在り方を考える議員連盟(野田聖子会長)が5日、不妊治療などのルールを定める特定生殖補助医療法案の要綱案をまとめた。当サイトではこれに先立ち、同議連の古川俊治副会長(参院自民党)を取材、生殖補助医療の手段としての代理出産と子宮移植に関する考えを聞いた。今回の法案で代理懐胎・代理出産は認められていないが、古川副会長は子宮移植による出産について法案と同時並行で進めるとした(取材日5月29日)。
◾️代理出産の子は生物学上の親子
特定生殖補助医療法案は、第三者の精子や卵子を使う生殖補助医療について規定している。具体的にはAID(Artificial Insemination by Donor=非配偶者間人工授精)、IVF-ET(In Vitro Fertilization– embryo transfer=非配偶者間体外授精・胚移植)、卵子提供に関するルールが定められる。
無精子症などの既婚男性が第三者の精子の提供を受けて夫婦の子供をつくる、あるいは高齢などで卵子が受精しにくい状態にある既婚女性に健康な卵子を提供して夫婦の子供をつくる場合に生じるであろう問題に備え、ルールを決めておく。
特に注目されるのは、たとえばAIDであれば、精子の提供を受けた夫婦にとって生まれた子供の父親は法律上の父親であるが、遺伝学上の父親は精子提供者であるから、生まれた子が「本当(遺伝学上)の父親を知りたい」と思った時にそれを知らせるための手続きをどうするかという点である。要綱案では医療機関から報告を受けたドナーの情報を、国立成育医療研究センターが100年保管し、子どもは成人になればセンターに情報開示を請求できる仕組みとなっている。
日本の特定生殖補助医療にとって基本的なルール作りという意味で法案の持つ意味は大きい。しかし、今回の法案に代理出産に関する規定が盛り込まれていないことに落胆する夫婦は少なくないと思われる。
上記のAIDなど3つの生殖補助医療で誕生した子は父か母の一方しか血が繋がっていないが、夫婦の受精卵を第三者の子宮に胚移植する代理懐胎・代理出産は、生まれた子は夫婦の遺伝子を100%受け継ぐ。法律上は親子ではないが、遺伝学上は紛れもなく親子である。
子を望む夫婦の中には、自分たちの遺伝子を受け継ぐ子の誕生こそを望む場合もあるはず。しかし、それを叶える代理懐胎・代理出産は日本では認められていない。はっきりと禁止する法律はないが、2003年8月に日本産婦人科学会が「代理懐胎に関する見解」を発表、「代理懐胎の実施は認められない。対価の授受の有無を問わず、本会会員が代理懐胎を望むもののために生殖補助医療を実施したり、その実施に関与してはならない。また代理懐胎の斡旋を行ってはならない。」と全面的に禁止している。
◾️代理出産の先駆けとなった高田延彦・向井亜紀夫妻
代理懐胎の禁止の会告が出た2003年の秋、プロレスラーの高田延彦さんとタレントの向井亜紀さん夫婦は代理出産を試み、米国で同国の女性に双子を産んでもらったことがメディアで大きく扱われた。その後、同夫妻は生まれた双子を実子として認めるように裁判で争ったが、最高裁は認めない決定をしている(最高裁小法廷決定平成19・3・23)。
今の時代、どうしても夫婦の遺伝子を持つ子供がほしいと思えば、高田夫妻のように代理出産を実施している国に行き、現地女性などに産んでもらう方法が数少ない解決法の1つである。米国、ウクライナ、ジョージアなどで代理出産をする夫婦が増えており、出生児数は既に100を超えるとされる(代理懐胎の是非 西希代子 ジュリスト1359号 p44 )。
海外での代理出産には莫大な費用が必要で、さらにウクライナではロシア軍の侵攻によって子供の引き渡しが決まらないという事態も生じている(日テレNEWS・【ウクライナ侵攻】”代理出産”で生まれた赤ちゃん “両親”への引き渡しが決まらず)。
高い医療技術を有し、安全な日本で代理出産ができるようにしてほしいという潜在的なニーズは、既に100人以上の子が誕生しているという事実からも一定数存在すると考えられる。
◾️産む負担を押し付ける非倫理性
同議連の古川副会長に代理出産が認められていない点について聞くと、夫婦の遺伝子を100%受け継ぐ子を望む場合、代理出産よりも子宮移植がベターであり、法案と並行して子宮移植の解禁を進める考えを示した。実際に議連では2022年11月25日の総会で子宮移植の現状と課題について専門家を招き説明を受けている(古川俊治オフィシャルウェブサイト・活動報告11月25日)。
古川副会長に、まず、代理出産がなぜ日本で認められないのかを聞いた。
ーー代理懐胎の実施が国内で認められないのはなぜでしょうか
古川副会長(以下、古川):よく言われるのは、産む負担を他人に押し付けることの非倫理性です。もう1つは法律関係が混乱する点にあります。たとえば、妊娠をしてほしいと頼まれた方が酒を飲んだらどうか、タバコを吸ったらどうか、その時に奇形の子供が出たらどうなんだという問題があります。今は法律上は特別養子縁組(民法817条の2参照)の制度を使っていますから、依頼夫婦の理想とする子供が生まれなかったから受け取らないという場合には制度が成り立たなくなります。逆に産んだ女性が子供が可愛くなって渡さないということも考えられます。また、現行の法律では産んだ女性が母親になりますが、その女性が結婚していたら、夫は全く関係ないのに父親になってしまいます。
ーー嫡出推定(民法772条1項)ですね
古川:そうです。そういうことを考えると、法律的に疑義がある制度になってしまいます。
ーー産む負担について、もう少しご説明ください
古川:他人に産むことを押し付ける非倫理性ですが「私は仕事をしていて忙しいから、私が産むのではなく、あなたが産みなさい」ということも起こり得るわけです。
ーー学会の会告では、代理懐胎の身体的危険性・精神的負担も禁止の理由として挙げています
古川:今まで女性は必ず自分の遺伝子を半分持った子を妊娠してきました。それは自然摂理です。それが(代理懐胎では)完全に自分と遺伝子が異なる子を妊娠することになるわけで、本当に安全なのかということです。そういう問題から我々としてはそうした実験的なことはトラブルが多すぎるのではないかということでやめようということを考えています。それともう1つ大きいのは子宮移植という方法が出てきていることです。
ここで古川副会長は子宮移植について触れた。
これは例えば先天的に子宮がないロキタンスキー症候群の女性や、前述の向井亜紀さんのように子宮頚がんで子宮を摘出した女性が、第三者から子宮を移植して、そこで妊娠するというものである。
これを解禁しようというのが古川氏の考えで、それによって子宮のない女性に子供を産み、育てる道を開こうというのである。
詳細は後編で。
(後編につづく)