飲む中絶薬条件緩和「1〜2年のうちに」日産婦
松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵
最新記事 by 松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵 (全て見る)
- 24年後もサバイバー 中島瑞果(2)生き残るために - 2026年2月11日
- 24年後もサバイバー 中島瑞果(1)PTA会長”みずっち” - 2026年2月8日
- 文化人放送局が認否保留 著作権侵害訴訟始まる - 2026年1月25日
国内初の飲む中絶薬「メフィーゴパック」の使用条件の緩和について、日本産婦人科医会の石渡勇会長が慎重な姿勢を示し、時期については1~2年必要との見解を明らかにした。9日、都内で行われた記者懇談会の場で話した。現在、入院可能な有床施設(病院または有床診療所)に限って使用が認められている「メフィーゴパック」を、無床の診療所が扱えるようになることを同医会としては望んでいるものの、報告・突合体制の徹底が必要との見解を示した。
◾️英製薬会社製造販売のメフィーゴパック
メフィーゴパックは妊娠中絶のための経口薬で、英ラインファーマ社が製造販売している。2つの錠剤を服用して妊娠中絶するもので、1剤目にミフェプリストンを投与。これは妊娠維持の阻害=妊娠を中断する作用がある。そこから36~48時間後に2剤目のミソプロストールをバッカル投与(歯茎と頬の間に錠剤を挟み、唾液でゆっくりと溶かす)する。こちらは子宮筋の収縮や子宮頸管の熟化が起き、胎嚢(受精卵を包む袋状の部屋のようなもの)を排出させる作用がある(懇談会配布資料・メフィーゴパックの特徴と薬剤承認後全国調査の結果について から)。
これまで日本での妊娠中絶は吸引法か掻爬法による外科手術によるしかなかったが、メフィーゴパックは飲み薬で中絶が可能になることから、その認可を歓迎する声はある。世界保健機関(WHO)もガイダンス「安全な中絶(Safe abortion)」で吸引法もしくは薬剤による中絶を推奨している。
こうしたことから2023年4月28日に製造販売が承認された。これに合わせて厚労省はメフィーゴパックの実臨床運用における注意事項を通知した。
①当面は入院可能な有床施設に限定した外来・入院運用
②指定医の面前で投与
③1剤目服用時点で妊娠9週0日かそれ以前
④院内における薬剤の厳重な保管(パック内の2剤は同一患者に投与)
⑤人工妊娠中絶報告票に経口中絶薬を使用した旨の記載、市販直後全例調査への協力
(以上、懇談会配布資料・経口中絶薬メフィーゴパックの市販後の現況について から)
この点で現在問題になっているのは①である。要はWHOも推奨する経口薬による妊娠中絶が、入院可能な有床施設に限られていることから、利用者が限られてしまうことを懸念する声がある。
◾️厚労省が緩和から一転差し戻し
2024年9月の薬事審議会ではいったんは無床診療所でも一定の要件を満たせば投与可能の方針を打ち出された。ところが、日本産婦人科医会から「使用実績がない県があることや医療機関での事務作業が膨大になること、講習の義務化・管理体制の効率化が必要となることから、無床の診療所での使用は時期尚早との指摘」を受け、「厚労省は緩和から一転、異例の審議差し戻しを決定」という事態になった。
具体的には日本医師会(松本吉郎会長)から薬事審議会に、無床診療所を対象とした講習会受講の義務化、薬剤の流通管理体制等のデジタル化、安全性確保のための資材、国民への正しい情報提供の4点が限定解除のために必要な事項であるとして申し入れが行われた。
これに対して、コラムニストの河崎環氏は「女性の間では(経口中絶薬は)非常に注目が高いなか、今回(手軽に)手に入るかもしれないと自由の光が見えた瞬間に、差し戻しになったのは失望が大きかった」とし、株式会社トーチリレー代表の神保拓也氏も「(経口中絶薬は)身体的、精神的、経済的負担も軽減する効果が見込まれていることから、基本的には使用条件緩和の方向で進めていってほしい」などと声をあげた(以上、TOKYO MX・国内初の飲む中絶薬「メフィーゴパック」使用条件の緩和はいつに?日本産婦人科医会会長「あと一年ぐらいかかる」)。
9日の記者懇談会はこの点について日本産婦人科医会としての立場を説明する場となった。質疑応答の場面では「(医療界は)条件緩和について進める責務があり、いつまでにするというのを示さないのは多様な選択肢を求めている女性への説明責任を果たせていないように感じる」と、厳しい質問も浴びせられた。
この点について石渡会長は「(現在でも)選択肢としては(経口薬での中絶も)あるわけですし、選択肢として重要だと思っています。それを普及させたいというのはありますが、いつになったらできるのか、はっきりとしたことは言えませんけれども1年、2年のうちにはと思っています」と話した。
飲み薬であるため安全性が高いとの印象を持たれがちであるが、2023年の解禁から2025年3月末までに6800パックが出荷され、それによる重篤症例12例が報告されている(懇談会配布資料・経口中絶薬市販後の運用に関する課題 から)。そうした重篤症例になった時に薬剤の講習も受けていない無床診療所が対応できるのかは疑問が残り、講習の義務化、重篤症例になった場合の速やかなバックアップ体制ができるまでは簡単には条件緩和できない事情はある。
◾️重要なデジタル化
メフィーゴパックの使用において特に重要なのが、報告・突合(とつごう)体制の徹底のために必要となる薬剤の流通管理体制等のデジタル化の部分。適法ではない中絶が行われるような事態は避けなければならない。そのためにメーカーが出荷してから、1剤目、2剤目ともに同一の患者に対して投与されるところまでを正確に把握できるシステムの構築が必要となる。
既にメーカーと日本医師会、日本産婦人科医会の間でその作業は進められているとの説明が懇談会の中でなされたが、十分なシステムができるまでには時間が必要となる。そのためにも直ちに条件緩和というわけにはいかない。
「薬剤が入荷されて使われた、そこがデジタル化の中で見える化されていかないと、どこにどういう風に流れていくか、そこには非常に懸念を持っています。それができずに1例でも2例でも、どこかに薬が行ってしまったということになると社会的に大変な問題になります。その意味でデジタル化は必要になります」と石渡会長は説明する。日本産婦人科医会としても普及はさせたいが、薬品の管理体制が十分に構築されない場合のリスクを考えれば慎重に構えざるを得ない事情がある。
◾️そもそも堕胎は犯罪という出発点
こうした問題の根には、日本における妊娠中絶の法的制度の難しさも関係している。そもそも堕胎は犯罪である。
【刑法212条】
妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する(2025年6月1日から懲役が拘禁刑になる)。
本来、違法な行為である堕胎が一定の要件を満たした場合に認められるのは、母体保護法14条で違法性が阻却され、堕胎罪には問われない制度になっているためである。
【母体保護法14条】
都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
1 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
2 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの
そうすると、女性には自己決定権に由来する中絶の権利があるという主張は、あるとしても無制約に認められるものではなく、抑制的なものとならざるを得ない。石渡会長はその点も意識し、条件緩和における慎重な姿勢について「社会的安全」というキーワードを口にする。
「堕胎罪(の違法性)を阻却するという意味で母体保護法指定医師が指定されています。指定医師は生命を断つという医療行為をやっているわけです。そして、指定医師以外の人間がやれば、罰せられます。そういう意味でも社会的安全を考えた時に慎重にやらざるを得ないと思っています」。
◾️社会的安全の真意
メフィーゴパックは経口薬であり、薬を飲むだけで堕胎できる。そうなると指定医師ではない者、たとえば中絶を希望する者がどこかから入手して自分で堕胎をした場合は刑法212条の堕胎罪が成立することになる。そのため、薬剤の管理(デジタル化)は違法な行為を許さないために絶対に必要な措置。
この点、堕胎の被害者は堕胎をする本人であり、被害者なき犯罪であれば、その行為を認めてもいいという考えも成り立つのかもしれない(実際、堕胎罪は胎児、母体を保護する趣旨とされる)。
しかし、安易に堕胎を認める社会は多くの女性の健康な肉体を傷つける。そのようなことが発生しないようにパターナリスティックな制約で女性を守っている、それが刑法212条の規定である。いわば、社会全体で女性を守るシステムであり、そのような社会の仕組みを安易に変えることで多くの女性が被害を受けることになりかねない。メフィーゴパックは使い方を間違えると、女性を守る社会制度を根底から崩しかねない破壊力を有している。石渡会長の言う社会的安全はそのような文脈で捉えるべきであろう。
国際的な観点からも、国内の事情からもメフィーゴパックは中絶を望む女性には福音となるのかもしれないが、大きなリスクも孕んでいる。慎重な扱い、さまざまなリスクを排除してからの条件緩和という決断は、妥当な判断であると思われる。






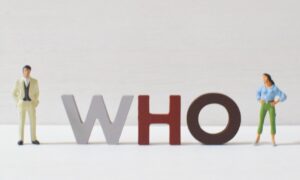


最も憂慮されるのは、本薬剤を第三者が妊婦に服用させる事態です。これこそが殺人罪に匹敵する真の堕胎罪であり、それを防ぐためにも薬剤の徹底した管理と医師の面前での服用は譲れない条件です。
現場の先生からの声と思料いたしますが、貴重なご意見をありがとうございます。
>>薬剤の徹底した管理と医師の面前での服用は譲れない条件
懇談会での質疑応答を聞いていましたが、その点の重要性をあまり意識していない記者が多いのではないかという印象を受けました。出てきたワードが「自己決定権」「女性にとって多様な選択肢」などで、パターナリスティックな制約で社会全体で女性を保護しているという仕組みへの理解が薄いというイメージを持ちました。「このままズルズルと条件緩和を認めないのではないかと疑われる」といった随分と失礼な問いかけもあったほどです。
メディアこそがそうした部分で遵法精神、公序良俗の維持などを含む社会通念にしたがった判断ができるようにならないといけないと感じています。マスメディアが総じてそのような判断をして報じていれば、このサイトの存在価値がなくなってしまいますが(笑)